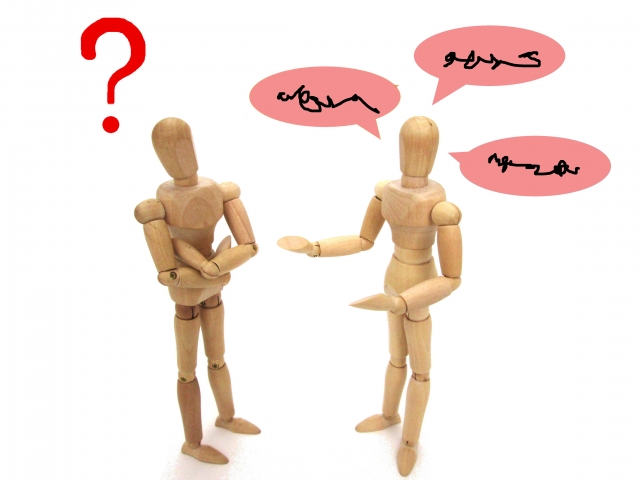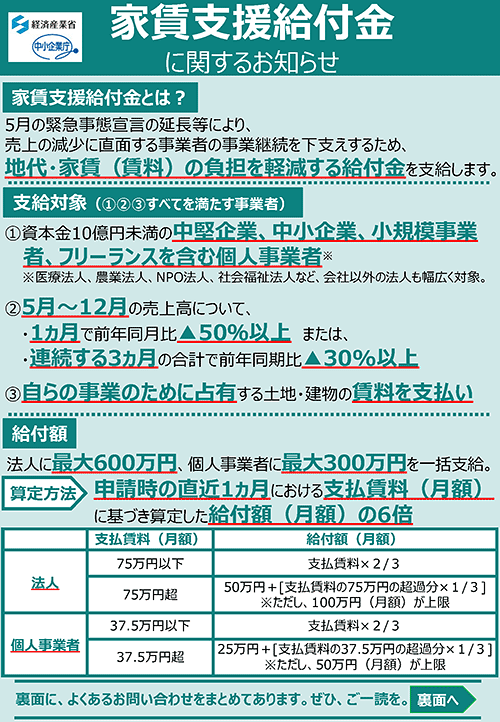こんにちは。中田麻奈美です。
このたびの西日本豪雨で大切な方を亡くされた皆様に心よりお悔やみ申し上げますとともに、
被災されたすべての皆様にお見舞い申し上げます。
本当に心までえぐられるような土砂崩れの爪痕を見るにつけ、
毎年のように起こる豪雨に対して何もできない自分が歯がゆい思いです。
命ある自分、何不自由ない自分ができることは何だろうと考え、
出来る協力は惜しまず復興に向けて応援していきたいと思っています。
初夏の眩しさに彩られる別れの影
実は、前回ブログからかなり間が空いてしまいましたが、
この間、私も大切な人を亡くしました。
商用ブログとして割り切って書けない私は、
執筆という感情があふれ出す作業を避けて、2週間が経ってしまいました。
そして今日、父の3年目の命日を迎えました。
ふと気づくと、もう3年も経っていた。
私にとって、初夏は緑輝く美しい季節であるとともに、
その命のきらめきの向こうに濃い影が差す季節となりました。
陰日向をくっきりと分かつ残酷なまでの陽光に、
あちらとこちらの世界の境界を見てしまうのです。

大好きだった伯母が残してくれた思い出の日々
享年88歳で逝った伯母。
最初に肝臓がんと診断されてから17年が経っていたといいます。
当然、私たちには病気のことは知らされることはなく、
治療がうまくいって、一度も手術することなく薬で抑えていられました。
昨秋に再発し、それからは1人暮らしもできなくなって、
入退院を繰り返していた伯母。
春には肺への転移が見つかり、
お腹の中に癌が散らばって腹水がたまるようになり、
最期は緩和ケアで穏やかな日々を過ごしました。
食欲が落ち、酢の物やアイスクリームくらいしか食べられなくなっても、
毎日従姉が差し入れる刺身を「美味しい美味しい」と8切れも食べて。
朦朧してうわごとを言うようになってからも、
「みんなが楽しそうにしてるのを見るのが一番うれしい」
「ありがとう ありがとう ありがとう」
そして危篤になってからも最期まで会話ができた伯母は、
「お母さんに会いたい…」との言葉を残し、
開いていた眼を静かに閉じて、
本当に眠るように逝ってしまいました。
多くの都会人にとっては信じられないことだと思いますが、私の母は9人兄弟の末っ子です。
母が生まれる前や幼いころに亡くなった兄弟もいて、実質6人兄弟として育ちました。
一番上の姉とは20歳くらい離れています。
遠くは東京や岡山など、住む場所はバラバラになっても、
盆正月には親戚中が集まり、それはそれは賑やかでした。
子ども世代の15人の従兄弟勢が、今でも仲良く付き合っています。
中でも亡くなった伯母は一番近くに住んでいて、
小さいころから行き来が多く、
祖母が亡くなってからは伯母がおばあちゃん代わりでした。
私たちにも厳しいことをズケズケ言ってくれて、
色々なお手伝いを経験させてくれて、
寄れば楽しい笑い話と美味しい手料理が待っていて(ドッサリ)
進学や就職、結婚、出産…と節目節目にはわが子のように喜んでくれて。
長女出産のときは、病室まで駆け付けてくれましたね。
辛いことがあっても、
鹿児島に帰ればみんなが待ってる。
絶対に味方だって信じられるぬくもりがある。
私はあまり人からどう思われるとか嫌われるとか気にならなくて、
「強いね」と言われることもあるけれど、それは親戚との強いきずなを信じているからだと思います。
価値観が揺るぎないと、行動に迷いはない
長野から鹿児島、毎年2~3回帰省するとなると、
普通にハワイくらい行けちゃうんじゃないかというくらいお金も時間もかかります。
それでも、家族や、伯母をはじめとする親族と過ごす時間はかけがえのないものでした。
圧倒的に、海外旅行より帰省が大切だった。
私にとって、親戚とのワイガヤ以上に価値のあることはない。
そう思えるくらい、楽しい盆正月を毎年繰り返してきて、
誰かの結婚式だの、法事だの、還暦や古稀の祝いだの、
もうとにかく何だかんだでいつも寄り集まって、
面白おかしい思い出が、ずっと私を支えてくれました。
だんだん大きな病気をしたり、足腰が弱っていく伯母たちと、
あと何回一緒に食卓を囲めるか分からないという気持ちはありました。
だから無意識に帰省を優先してきたかもしれません。
生きているうちに、会いたい。
葬式に駆け付けたって何の意味もない。
緩和ケアに入り、余命1か月と聞いたとき、
1週間でも早く、と仕事を蹴って新幹線を手配しました。
家族、親戚が一番大事。
この価値観が揺るぎないものだったから、
無理やりすぎる日程で、普通だったら組まない旅程でも迷わず駆けつけました。
だけど、
間に合わなかったのです。
出発当日の朝、危篤の連絡があり、
名古屋に向かう特急の中で訃報が入りました。
泣くに泣けなかった。
あと7時間頑張ってくれたら…
父のときと同じ虚しさ。
長野は遠すぎる。
「また来るね」って言って別れた夏の日、
あの時はまだ車まで見送りに出てくれて、
見えなくなるまで手を振ってくれたのに。
「また来るね」って言ったのに。